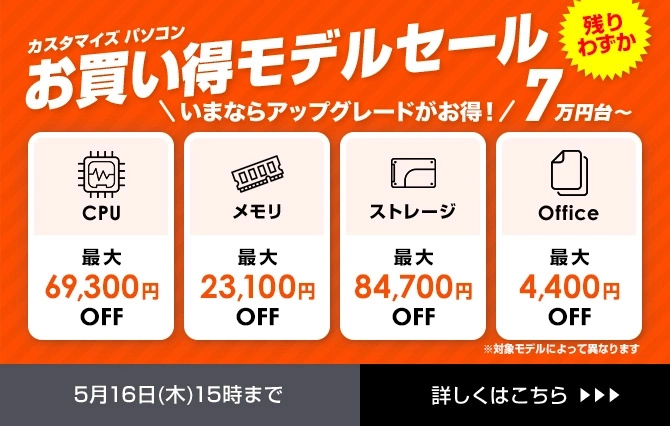SSDとHDDを使い分けるポイント
2台内蔵で快適な大容量ストレージに
2024.04.30(TUE)
2024.04.30(TUE)
ストレージのSSDとHDD、それぞれの特長を活かした使い分けで、パソコンの快適性を向上させることが可能です。ストレージの性能と容量のバランスを取り、パソコンを快適に使いこなしましょう。SSDとHDDの使い分け方を解説します。
SSDとHDDの違いをわかりやすく解説
パソコンのストレージであるSSDとHDDは、データを記録するという役割こそ同じものの大きな違いがあります。それぞれ仕組みに大きな違いがあり、それによって使い方が変わります。SSDとHDDの違いを見ていきましょう。
SSDの特徴
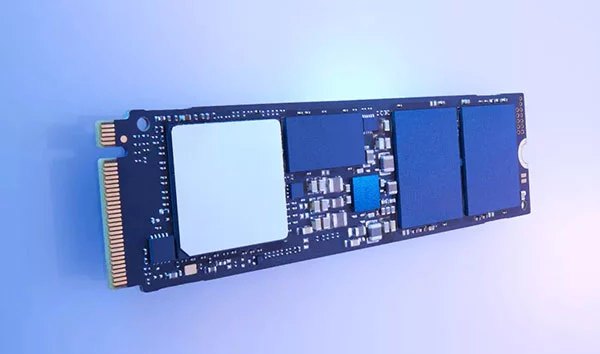
SSDの最大の特徴は、フラッシュメモリへ電気的に記録する仕組みになっているため、内部に物理的な動作を行う部品がないことです。そのため、大きな動きや衝撃があっても故障しにくく、もしパソコンを落としてしまったとしても大きなダメージを受けずに済みます。
また、物理的な動作がないため、動作中の騒音がほとんどありません。耳障りな音を感じることなく、作業に集中できるのです。さらにデータへのアクセスが高速で、Windowsやソフトの起動、データの読み書きが非常にスムーズになります。
ストレージとしてSSDは非常に優秀なのですが、価格の高さが欠点です。そのため、大容量のSSDを搭載しようとすると、パソコンの価格に大きく影響してしまいます。また、書き込み回数に限界があるため、長時間にわたって使用していると、寿命を短くしてしまうおそれがあります。
SSDのメリット、デメリット
SSDにはさまざまな特徴があります。この特徴を整理して、メリットとデメリットに分けて解説します。SSDとHDDを活用するときは、このメリットとデメリットをしっかりと踏まえて考えることが大切です。
メリット
SSDのメリットは、次のとおりです。
- データのアクセスが高速
- 動作音がなく静か
- 物理的な衝撃に強い
- 発熱量が少なく、熱によるトラブルを減らす
何よりもSSDの最大のメリットは、データアクセスの速さです。パソコンの起動時間を大幅に短縮するほか、ソフトの起動、データの読み込み・書き込みが格段に速くなります。頻繁にファイルを開いたり、保存したりする作業のときは、SSDのメリットを実感できるでしょう。
また、物理的な動作がないため、SSDは動作音が非常に静かなほか、衝撃などにも強いのもメリットです。発熱が少ないため、パソコンの熱によるトラブルを減らすこともできます。
デメリット
デメリットとして考えられるものには、次のものがあります。
- 価格が高い
- アクセス回数が多いと寿命が縮む
- 故障時のデータの復旧が困難
価格の高さはSSDの最大のデメリットです。HDDと比べると同容量のSSDは高価なため、数TBもある大容量ストレージを搭載するのは難しいでしょう。また、SSDはアクセス回数に制限があり、頻繁にデータを書き替えるような用途だと、寿命を短くしてしまうおそれがあります。
SSDは電気的に記録する仕組みのため、故障してもデータを復旧できないことがあります。そのため、定期的なバックアップが欠かせません。
HDDの特徴

HDDは長年にわたって、パソコンのストレージとして使用されてきました。いまでもHDD=ストレージという認識の人も多いでしょう。
HDDの内部にはデータを記録する磁気ディスクがあり、ヘッドという部品でデータへアクセスします。
HDDの特徴は、コストパフォーマンスの高さです。同じ価格で比較すると、SSDよりはるかに大容量のHDDを購入できます。大容量のデータを保存する用途や、費用を抑えたいときにHDDは適しているといえるでしょう。
しかし、HDDは内部の部品が物理的に動作してデータへアクセスする仕組みのため、衝撃に弱いという欠点があります。強い衝撃を受けると、データを損失するリスクがあるのです。また、データのアクセス速度がSSDに比べると遅く、動作音や発熱もあります。
HDDのメリット、デメリット
いまやストレージの大半はSSDになっていますが、それでもHDDが利用されているのは、小さくないメリットがあるためです。長くストレージの主役として活躍してきたHDDのメリットとデメリットを見ていきましょう。
メリット
HDDのメリットをまとめると、次のようになります。
- 容量あたりの価格が安い
- 故障によるデータ復旧が可能
- 大容量ストレージがある
HDD最大のメリットは、コストパフォーマンスの高さです。同じ金額で比較すると、SSDよりもはるかに大容量のストレージを購入できます。大きなデータを扱う人であれば、HDDを選択することで大きく費用を抑えられます。
また、HDDは物理的にデータを記録しているため、故障したとしても専門の業者に依頼することでデータを復旧できることがあるのです。必ず復旧できるとは限りませんが、SSDよりも復旧できる可能性があります。
また、10TBを越える大容量HDDが一般的に流通しているため、大容量のストレージを求めている人にも適しています。
デメリット
HDDのデメリットには、次のものがあります。
- SSDと比べてアクセス速度が遅い
- 物理的な衝撃に弱い
- 動作音や発熱がある
- 寿命がSSDより短い
HDDはストレージとして遅くないものの、SSDと比べると格段にアクセス速度が劣ります。また、物理的な動作でデータへアクセスするため、衝撃に弱い、動作音がする、発熱があるなどの欠点もあります。ノートパソコンのように持ち運ぶ人にとって、HDDの衝撃の弱さは小さくないデメリットです。
また、寿命もSSDと比べるとHDDのほうが短いといわれています。
こういった背景もあり、ストレージの主流はHDDからSSDへと移っていったと考えられます。
SSDとHDDの使い分け方のポイント

SSDとHDDの特徴、メリットとデメリットを理解したうえで、上手に使い分けることが、パソコンの性能を最大限に活かすカギになります。どのようにSSDとHDDを使い分ければよいのか、使い分け方のポイントを解説します。
【動画・画像編集】動画・画像データはHDDへ保存
動画編集や画像編集では、大量のデータを扱います。これらの大量のデータをSSDに保存していると、あっという間にいっぱいになってしまいます。また、SSDは価格が高いため、増設の費用も割高です。
こういったときは、HDDのコストパフォーマンスのよさがいきてきます。ソフトはSSDへインストールして、データをHDDと使い分けるのです。数TBもの大容量ストレージがあれば、残りの容量を気にすることなく、大量のデータを保存できるでしょう。特に途中経過も含めて、複数のファイルを作成するようなときにおすすめです。
HDDはアクセス速度でSSDに劣りますが、残り容量を気にせず作業に集中できるのは大きなメリットになるでしょう。
【ゲーム】大作とカジュアルゲームで使い分け
ゲームを楽しむ場合でも、SSDとHDDの使い分けが重要です。特に大作ゲームは大容量なうえに頻繁にアクセスが発生するため、SSDへのインストールがおすすめです。SSDを利用することで、ゲームの起動やデータのアクセスが速く、快適なプレイが可能になります。
ただし、SSDは容量に限りがあるため、遊ばなくなったゲームはアンインストールして、空き容量を確保する必要があります。
一方で、ゲームのセーブデータやカジュアルゲームは、SSDほどの高速アクセスは必要ないため、HDDを利用するとよいでしょう。特にカジュアルゲームは一般的にファイルサイズが小さく、起動時間も短いため、HDDでも快適にプレイできます。
【書類作成・動画再生】SSDとクラウドストレージ
書類作成や動画再生のような日常的な使用では、SSDの利用がおすすめです。書類作成に使うオフィスソフトなどは、SSDにインストールすることで快適に動作して作業効率が向上します。
また、作成した書類データは、クラウドストレージへの保存がおすすめです。クラウドストレージであればインターネット経由で、どこからでもデータへアクセスできます。そのため、スマートフォンやタブレットのような、異なるデバイスでも書類データを開いて作業できます。
クラウドストレージはSSDなどのストレージが故障したときの、データのバックアップ先としても有効です。
SSDとHDDの2ドライブ内蔵のすすめ

パソコンにSSDとHDDのふたつのドライブを内蔵することで、それぞれの特長を活かした使い方が可能になります。パソコンの使い方の幅が広がる、SSDとHDDの2ドライブ内蔵について解説します。
SSDとHDDの2ドライブ内蔵とは
SSDとHDDの2ドライブ内蔵とは、ひとつのパソコンにSSDとHDDの両方を搭載することです。2ドライブ内蔵により、SSDの高速なデータアクセスとHDDの大容量のメリットを同時に得られます。
SSDにはWindowsやよく使うソフトをインストールし、HDDは大量のデータ保存用として活用します。
2ドライブ内蔵のメリットは、Windowsやソフトの起動速度が大幅に向上しつつ、大容量による大量のデータ保存も可能になることです。しかもストレージを内蔵しているため、データのやり取りも非常にスムーズです。
このようにSSDとHDDを2台内蔵することで、パソコンのパフォーマンスを向上しつつ、大容量のストレージを実現します。
外付けと内蔵ストレージの違い
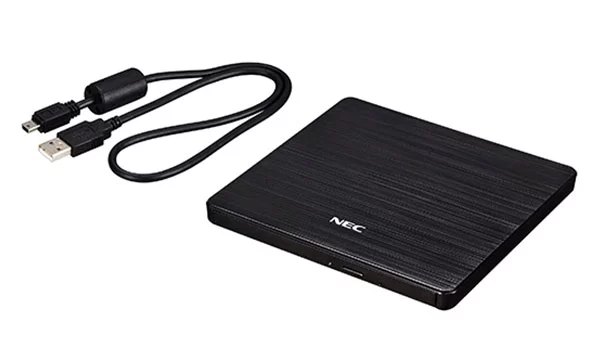
ストレージにはパソコンに内蔵するものと、USBなどで接続する外付けするものがあります。
内蔵ストレージはパソコンそのものに搭載しているため、接続などの面倒がありません。そのまま使用できるうえに、データ転送速度が高速なため、ストレージ本来の性能を発揮できるでしょう。
それに対してと外付けストレージは、接続の手間がかかるうえに、データ転送速度が接続方法に左右されます。また、使用中にケーブルが外れるリスク、パソコンと一緒に持ち運ぶ面倒などもあります。
ちなみに、外付けストレージにソフトをインストールすると、さまざまな不具合の生じるおそれがあるため、おすすめできません。基本的にソフトのインストールは、内蔵ストレージに行いましょう。
2ドライブ内蔵のメリット
パソコンにSSDとHDDの2ドライブを内蔵することで、高速なデータアクセスと大容量を同時に利用できるメリットが得られます。しかもそれが、大容量SSDのような、高価なストレージを購入することなく実現できるのです。
高速アクセスが求められるソフトや頻繁に使用するデータをSSDに、サイズが大きなファイルをHDDにと使い分ければ、それぞれのメリットを大きく受けられます。
また、HDDを緊急のバックアップ先として使用することもできます。特に大切なデータを両方のストレージに保存することで、いざというときのトラブルに備えられるのです。
2ドライブ内蔵のデメリット
SSDとHDDの2ドライブ内蔵は、メリットばかりではありません。デメリットもあることに注意して下さい。
ふたつのストレージを使い分けるのは、初心者にはやや複雑に感じられるかもしれません。知らず知らずのうちに、どちらか一方にソフトやデータが大量に保存される事態も考えられます。適切にデータを管理する面倒さは、デメリットといえるでしょう。
また、ふたつのストレージを内蔵することで、パソコンの価格も高くなります。ほかにも、HDDのアクセスの遅さが気になることもあるでしょう。SSDとHDDの両方のメリットだけでなく、それぞれのデメリットも抱えることに注意して下さい。
対応モデルならノートパソコンでも可能
2ドライブ内蔵はケースの大きなデスクトップパソコンだけでなく、対応モデルであればノートパソコンでも可能です。SSDは小さな基板のタイプが一般的なので、HDDを搭載するスペースがあるのです。HDDと同じサイズのSSDであれば、SSDによる2ドライブ内蔵も可能になります。
これによりSSDの快適さとHDDの大容量というそれぞれのメリットを、ノートパソコンでも得られます。
ノートパソコンを頻繁に持ち運ぶ人の場合、HDDが衝撃で故障したり、データを破損したりするリスクに注意が必要です。持ち運ぶ機会が多い人は、2ドライブ内蔵は避けたほうがよいかもしれません。
寿命のタイミングが違うことに注意
SSDとHDDはそれぞれ、製品としての寿命が異なることに注意しましょう。一般的にHDDはSSDよりも早く故障する傾向があります。これは、HDDが内部に物理的に動く部品があるためです。また、物理的な衝撃を受けて故障することもあります。そのため、2ドライブ内蔵の場合、HDDが先に故障してしまうことが多いでしょう。
ストレージが故障した場合、ストレージを交換するか、パソコンを買い替えることになります。HDDの短い寿命にパソコンを買い替えるタイミングが左右されてしまうことには注意が必要です。また、故障に備えてバックアップを取るように心がけましょう。